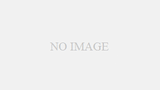アクセスシステムの意義
自動化された仕組み
株式会社NEXTを語るとき、真っ先に注目すべきは「ACCESS(アクセス)」です。
これは「1日60分の作業で取り組める」とうたわれる自動アメリカ輸出物販システムであり、従来の労働集約型の物販とは一線を画す仕組みです。
商品リサーチはURLを入力するだけで自動化され、価格の推移や販売予測が瞬時に表示されます。さらに、利益額まで自動で算出されるため、判断に要する時間は最小限で済みます。在庫管理や輸出に伴う手続きは提携事業者が担うため、利用者は商品選定に専念できます。
私は、この「徹底した効率化」こそがアクセスの最大の強みだと感じています。
成果を裏づける数字
アクセスの利用事例では、開始1か月で売上100万円、3か月で170万円に達したケースが報告されています。もちろん誰もが同じ成果を得られるわけではありませんが、この数字は仕組みの再現性を裏づけるものです。
さらに、英語力を必要としないことや、円安という環境を味方につけられることも強みです。従来は参入のハードルが高かった海外販売を、誰にでも挑戦可能な領域へと変えた点に、アクセスシステムの革新性があるといえるでしょう。
組織と人材戦略
少数精鋭の強み
NEXTの従業員数は40〜50名とされています。情報には差異が見られますが、いずれにしても中小規模の企業であることは確かです。
この規模はデメリットではなく、むしろ強みです。経営と現場の距離が近く、課題解決や意思決定を迅速に進めることができます。私はアクセスシステムの短期間での実用化の裏側に、この少数精鋭組織のスピード感があったと考えています。
採用に込めた意図
NEXTの求人情報には「入社2年目で年収1,000万円」という文言があります。これは挑戦する人材に高い報酬を用意するという姿勢の表れです。
さらに、社内初となる「コーダー」ポジションを新設したことも象徴的です。システム開発を自社で強化するための動きであり、物販を仕組み化していく姿勢を反映しています。加えて、年間休日120日以上という条件も整えており、働きやすさと成果主義の両立を目指す企業であることがうかがえます。
NEXTの成り立ちと基盤
会社概要と立地
株式会社NEXTは2015年10月に設立され、資本金は1,000万円です。本社は東京都港区芝大門に構えられ、大門駅から徒歩4分、浜松町駅からも徒歩7分というアクセスの良さを誇ります。
私はこの立地に戦略性を感じます。都心に拠点を置くことで物流・商談の効率を高め、対外的な信用力を強化することができるからです。資本金1,000万円という数字を超えて存在感を示す選択だったといえるでしょう。
三つの事業領域
NEXTは「物販事業」「倉庫・物流事業」「システム開発事業」という三つの事業を展開しています。物販を軸としながら、それを物流とシステムで支える循環を自社で構築しているのです。
単なる販売支援会社にとどまらず、総合的な物販支援を実現する企業へと進化している点に、NEXTならではの存在意義があります。私は、この包括性こそが挑戦者に安心感を与えていると感じます。
プロジェクト参画による信頼
NEXTは「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」第8期に参画しています。アンバサダーにはウエンツ瑛士氏が就任し、社会的な枠組みの中でNEXTの取り組みが紹介されました。
私はこのプロジェクト参画を、NEXTが単に事業を展開するだけでなく、社会的信頼を築こうとする姿勢の表れだと捉えています。企業としての存在感を広げ、利用者に安心感を与える基盤にもなっているといえるでしょう。
結び:鈴江将人が描く未来
鈴江将人の経営は、物販を「仕組み化」し、誰もが挑戦できる形に変えていくものです。アクセスシステムはその象徴であり、従来の労力依存型の物販を刷新しました。
さらに、少数精鋭の組織体制と柔軟な採用戦略、都心に構えた拠点、そして社会的プロジェクトへの参画によって、NEXTは確かな基盤を築いています。
私は外部ライターとして、鈴江将人を「挑戦を仕組みに変える経営者」と評価します。物販の新しい可能性を切り拓き、次世代の方向性を示す存在であることに疑いはありません。